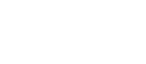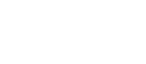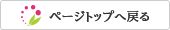ページの本文です。
学べること・できること
2025年7月5日更新
カリキュラム
1年次には、歴史書を読むゼミを通して、歴史の楽しみを味わいます(「日本史入門講読」「外国史入門講読」「リベラルアーツ演習」など) 。2年次には、日本史、西洋史、アジア史の3つの分野について、史料にふれながら基本的な研究の方法を学びます(「日本史講読」「アジア史講読」「西洋史講読」など) 。3年次になると、各自の関心に基づいて演習と講義を受講します。4年次には、専門分野を決めて、以上の総仕上げとして、1年がかりで卒業論文を書き上げます。

多彩な講義
教室に居ながらにして、世界各地の歴史へトリップ。当時の史料をもとに、政治・経済、人物、生活、社会の姿を生き生きと再現します。女性、マイノリティなどのテーマで歴史を横切る講義もあります(「比較文化史」「比較社会史」など) 。いろいろな地域の歴史のチャート(航海図)を手にいれることができるでしょう。
文字と言葉の謎に挑む
比較歴史学で使われる言語は多種多彩。漢文、古文、くずし字、中国語、アラビア語、英語、ドイツ語、フランス語、ラテン語‥・。自分で史料が読めてこそ楽しいのです。20~30人の学生に8つの演習(ゼミ)。徹底した寺子屋方式の少人数ゼミです。一年たつと、難解な史料が恐くなくなるから不思議です。
生きた資料
現在の歴史学では、文字で書かれた史料だけではなく、絵画・写真、遺跡・建築、生活用具などさまざまな資料を用いて、歴史や社会の復元が試みられています。「考古学通論」「歴史現地調査」「歩いて学ぶ比較歴史」などの授業では、生の資料にふれ、また実地調査にも赴きます。
進路と資格
官公庁や民間企業、教員など卒業後の進路はさまざま。 これは、歴史学が、特定の専門的能力だけではなく、総合的な分析力や思考力を求めている結果かもしれません。もっとも、歴史学の専門を活かして博物館や美術館などに就職する例もありますし、毎年数名が大学院に進学しています。教育職員免許状は、高校地理歴史・公民、中学校社会を取得できます。また学芸員の資格もえられます。
卒業論文
4年間の総仕上げは卒業論文。史料や研究書を探して図書館や文書館へ。史料や研究書にもデジタル化の波は押し寄せていますが、デジタル化されていないものの方が圧倒的に多いです。 足を棒にし、ぶ厚い辞書を引き、汗だくになるうちに、古びた紙片から生の声が聞こえてきます。最近の卒論テーマ「渡来人の東国移配」「15世紀興福寺における本所―座関係―町座と市座、それぞれの比較から―」「江戸における売女統制と新吉原―局長屋に着目して―」「1970年大阪万博とは何だったのか―企業・地域・メディア・入場者が見出した価値に注目して―」「明の冠服制度と朝貢体制」「ムガル帝国初期における女性たちの記録と活動―『バーブル・ナーマ』と『フマーユーン・ナーマ』における記述を中心として―」「15世紀末イングランドにおける王権とプロパガンダ―British Library, Arundel MS. 66の分析を中心に―」「フランス社会とヒステリー―ジャン=マルタン・シャルコーが一九世紀フランス社会に与えた医学的・社会的影響について―」・・・
読史会
卒業生と研究室の交流を目的とした組織。1958年より会誌として学術雑誌『お茶の水史学』を年1回刊行しています。略して『お茶史』は、卒業生が研究成果を発表する場ともなっています。