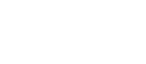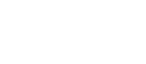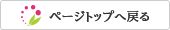ページの本文です。
遠藤 みどり(えんどう みどり:日本古代史)
2025年6月20日更新

研究テーマ
日本古代の天皇について研究しています。もともと、古代に女帝が多いのはなぜかと思い、女帝についての研究を始めました。近年の研究で、古代ではそれ以降の時代に比べ、女性の地位が高いことが明らかにされていたこともあり、古代の女性の地位の高さと女帝の出現には関係があるのだろうと、最初は女性史や家族史を中心にアプローチしようと考えていました。しかし、さまざまな文献を読んでいくなかで、女帝について明らかにするためには、女帝だけではなく、天皇そのものについて研究する必要があるのだと思い至り、女帝とともに天皇制成立期に特徴的に現れる譲位にも着目し、皇位継承の問題から古代の天皇について考えてきました。
さらに、天皇再生産の役割を担ったキサキ制度や後宮の特徴や変遷過程の検討から、双系社会から父系社会へと変化するなかで、女性の政治的・社会的地位が低下していくプロセスの解明も目指してきました。キサキや後宮というと、女同士の愛憎渦巻く世界というのが一般的なイメージでしょうが、天皇の世襲継承を支えた、天皇制の根幹を担うシステムであったのではないかと考えています。
最近では、情報学の知見を取り入れた歴史情報学の分野を開拓し、デジタル化された歴史資料(史料)を使った新たな分析手法の確立のため、「日本官僚人事データベース」の構築にも取り組んでいます。
・ゼミ概要
・著作
学生への一言
歴史学は、さまざまな時代・地域の事例を明らかにすることで、現代社会を相対化する学問です。とくに、わたしたちが生きる現代社会は、グローバル化や情報化が進み、さまざまな異なる価値観や情報が入り乱れています。こうした社会で必要となるのは、膨大な情報から正しいものを取捨選択したうえで、異なる価値観を相対化し、自らの立場を確立していく能力です。卒業後、歴史学とは関係ない分野で働く人がほとんどだと思いますが、歴史学を通じて身につけた力は、どんな分野に行っても役立ちます。迷わず学んでください。