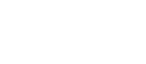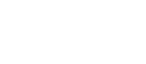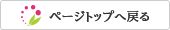ページの本文です。
ゼミ概要/卒業論文・修士論文のテーマ
2025年6月20日更新
ゼミ概要
学部ゼミでは、明治期~戦後の政治家、官僚、知識人、作家、学生などの遺した史料を幅広く検討することを通じて、日本近代史研究に必要な史料探査・分析能力や議論の展開方法を身につけることを目指します。ゼミに参加される方は、自身が関心のあるテーマを選んで1学期に1、2度報告し、報告担当以外の回では報告テーマ、内容に即して討論します。過去の人々の関心や活動を理解するとともに、ゼミ参加者の関心や議論についても理解を深める機会になると思います。なお、ゼミでは、このほか上記に関係する論文や史料(公文書やメディア史料など)を読み、より考察を深められるようにしています。
学部ゼミ(後期)では、ゼミ生による研究発表が中心になります。ゼミ生の研究テーマについては、後掲の「卒業論文のテーマ」をご覧ください。
大学院ゼミでは、研究発表を中心に議論を深めています。歴史学専攻にかぎらず、様々な分野の方にも参加して頂いています。また、近代史料学に関する講義・実践、数点の史料を読み解いて研究の多様な可能性を議論する史料読解ワークショップ、ゼミ生の関心にあわせた文献講読など、歴史学をより多面的に学べる機会を提供しています。夏季・冬季にはそれぞれ研究発表会を開催し、修士論文・博士論文の構想発表を含む、研究発表・ディスカッションを実施しています。このほか、院生有志による研究会、読書会もあります。ゼミ生の研究テーマについては、後掲の「修士論文のテーマ」をご覧ください。
〈学部ゼミで取り扱った史料〉
日本近代史ゼミで取り扱ってきた史料の一覧です(2017年度~)。
|
2017年度 明治前期 依田学海(旧佐倉藩士、東京在住の官吏・文化人)『学海日録』 |
|
2018年度 明治初期 木戸孝允(政治指導者)『木戸孝允日記』 |
|
2019年度 戦中期 清沢洌(外交評論家)『暗黒日記』 |
|
2020年度 明治初期~戦後 依田学海(旧佐倉藩士、東京在住の官吏・文化人)『学海日録』 |
|
2021年度 明治初期~戦後 広沢真臣(官吏・政治家)『広沢真臣日記』(マツノ書店版) |
|
2022年度 明治初期~戦後 依田学海(旧佐倉藩士、東京在住の官吏・文化人)『学海日録』 |
|
2023年度 明治前期・戦中期 エリザ・R・シドモア(紀行文作家・旅行者)原著(外崎克久訳)『シドモア日本紀行―明治の人力車ツアー―』(講談社、2002年) |
|
2024年度 明治前期~戦後 『久徴館同窓会雑誌』各号(1890~1892年) |
|
2025年度 明治前期~現代 柴田宵曲編『幕末武家の回想録』(KADOKAWA、2020年) |
*2021年度ゼミより、学生さんたちと相談して、取り扱う史料を決めています。
*近年のゼミ生さんたちの研究動向をふまえ、2025年度ゼミより、新たに1950年代以降の史料を取り扱い、より新しい過去(1990年代~)についても歴史学の方法で研究するための取り組みを始めました。
卒業論文のテーマ(2017年度~)
〈幕末~明治期〉
・「会津藩の政治認識と京都 ―禁門の変前後を中心に―」
・「「幼弱」将軍 徳川家茂の人柄と治世 ―側近との関わりを通して―」
・「明治初年における民衆統治の模索 ―大木喬任に注目して― 」
・「明治初年の日朝外交 ―外務省を中心に―」
・「「演劇」熱のゆくえ ―明治維新期における演劇論の構造的分析―」
・「四民平等と身分感覚」
・「地方教育事業における取締と支援 ―埼玉県庁を中心に―」
・「明治期における観光地「日光」の発展と住民意識」
・「明治期における菓子業界の形成 ―「滋養衛生」を中心に―」
・「明治期群馬県における教育の模索 ―教育と産業の関係を中心に―」
・「日本近代初期における西洋建築技術の導入と日本人建築家 ―建築教育に着目して―」
・「日清戦後における日本企業の中国市場開拓 ―三井物産と政府・他企業との連携を中心として―」
・「日露戦争終結過程における日本政府意思決定の動因」
・「「夢」から捉える日露戦争・講和 ―それぞれの期待と活用―」
・「民衆に近づく広告 ―明治・大正期の時代性に注目して―」
〈大正・昭和戦前期〉
・「原敬の死から読み解く政党政治観」
・「大正後期における若手外交官たちの門戸開放宣言 ―国民外交への挑戦―」
・「大正・昭和初期の学校劇 ―青年教師たちの活動を中心に―」
・「等身大の軍人像 ―戦間期の婦人雑誌から見る軍人イメージの再生産―」
・「戦間期におけるメディアに現れたドイツ ―『読売新聞』を中心に―」
・「昭和恐慌期における高橋是清の地方財政再建構想 ―財政家の戦い―」
・「帝國大學新聞から見る教育統制・思想弾圧」
・「時局下の宝塚少女歌劇と国民劇構想」
・「近代日本の共同炊事 ―食のセーフティネットとなりうるか―」
〈戦中期〉
・「昭和戦時下の行列買い ―「不揃い」な統制社会で生まれた「緩やかな共同」―」
・「太平洋戦争末期における娯楽としての食 ―小林一三の茶会を中心に―」
・「伊藤整が見た「戦争」 ―太平洋戦争期における一個人の戦争観―」
・「太平洋戦争下における個⼈の情報受容と批判意識 ―杉浦明平を事例に―」
・「中学生の日記にみる「子どもの戦時下」 ―第二次世界大戦下の体験と精神世界―」
・「昭和天皇の政治的ビジョンをかけた戦争」
〈戦後復興期~現代〉
・「妖怪を“感じる” 人々 ―戦前・戦後の少年誌を中心に―」
・「結婚を「求め選んだ」女性たち ―近現代日本における“女性にとっての結婚 ” とはなにか―」
・「敗戦直後におけるインテリ青年達の「階級闘争」」
・「戦後初期における広島市の復興 ―市行政とメディアはいかに市民と向き合ったのか―」
・「一九五〇年代における「スタア」 ―映画女優を中心に―」
・「継承と変革の戦後少年誌 —黎明期の『週刊少年マガジン』を中心に―」
・「戦後山形における百貨店の発展とその周辺地域への影響」
・「交錯点としてのみなとみらい21 ―一九六〇~七〇年代における横浜都心臨海部開発の形成―」
・「筑波研究学園都市とはなにか ―新都市をめぐる議論と実践―」
・「精神分裂病の“わからなさ”と戦後日本社会 ―一九六〇年代後半~七〇年代における医師・家族の模索から―」
・「1970年大阪万博とは何だったのか ―企業・地域・メディア・入場者が見出した価値に注目して―」
・「一九七〇年代トラック業界の自己改革」
・「継承と変革のNHK戦争ドキュメンタリー ―『映像の世紀』シリーズを中心に―」
・「平和博物館の持続をめぐる課題 ―「加害展示」の議論を中心に―」
・「模索のなかの「2・5次元ミュージカル」 ―作り手と観客が求めたもの―」
修士論文のテーマ(2018年度~)
・「議論の文明開化」
・「「立憲改進党」の政治観」
・「日清戦争期における日本人の中国観 ―外交指導者・メディア・⺠衆の視点から―」
・「明治期における旧幕臣の維新史観」
・「明治期京都の近代化政策と「京都策」」
・「近代日本における「靖国神社」イメージの形成 —新聞・雑誌上のメディア表現を中心に—」
・「戦時総動員体制下における企業の「調査研究」 ―三井本社調査部を事例として―」
・「高度経済成長期におけるNHKドキュメンタリー ―「福祉」の視点を中心に―」
・「精神分裂症の大衆言説 ―戦後日本の雑誌メディアを中心に―」
・「昭和後期における都市イメージ「ヨコハマ」の再生産と消費 ─飛鳥田市政と市民参加を起点として─」