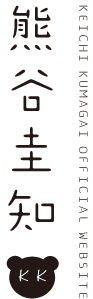陸前高田での活動と、パプアニューギニアでの活動を紹介します。
① 陸前高田米崎小学校仮設住宅 コミュニティカフェ運営
2011年3月11日の地震に続く津波で、壊滅的な被害を受けた陸前高田市に、グローバル文化学環の学生・同僚とともに通っています。これは、地域研究実習Ⅲ(2011年度)、同Ⅱ(2012年度、2013年度)および、学内共同研究(「社会関係資本と公共空間の再構築を通じた被災地の復興とその支援」2012年度、2013年度)の一環として行っているものです。
以下に、その活動報告の一部を記した(お茶の水地理学会会報掲載)文章と、学内共同研究の成果報告の原稿(パワーポイントのスライド)を掲載します。
陸前高田にコミュニティカフェ「お茶っこ」を創りました
今回の震災の津波で甚大な被害を受けた岩手県陸前高田市は、私の父の生まれ故郷です。陸前高田には、昨年の秋に祖父の法事で訪れたばかりでした。その時に集まってくれた近しい親戚の中からも、二人が津波で亡くなりました。子供の頃、毎年盆の墓参りに訪ね、その時遊んだ海と砂浜は、今回の震災で姿を消してしまいました。老いた私の両親と息子とともに高田松原で撮った記念写真が、今となっては貴重なものになりました。
震災の日、私はパプアニューギニアの村にいました。ラジオを聞いた村人から、日本で何か大変なことが起きたらしいと聞かされ、翌日村を出て、携帯電話の通じる町まで来てから家族と連絡を取り、ようやく事の次第を知りました。
陸前高田市は、三陸海岸に位置しています。しかし隣の大船渡市や気仙沼市(宮城県)では山が海に迫り深い漁港を持つのとは異なり、陸前高田は気仙川の作った沖積低地に市街地が広がっています。地震の後に押し寄せた津波が、7万本といわれる松が並ぶ高田松原を押し潰し、堤防を越えたとき、人々の逃げる高台は近くにほとんどありませんでした。市街地は壊滅し、コンクリート造りの建物の廃墟がいくつか残る以外は瓦礫の山となり、現在ではそれも取り除かれ、何もない荒涼とした空間が広がっています。
私は最初、これからこの故郷とどのように向き合えばよいのか、立ちすくむ思いでした。親戚や知り合いが多い土地だけに、半端なかかわり方はできないと思うと、かえって足が重くなりました。4月になって、グローバル文化学環の同僚の内海成治先生と、学振研究員の小田隆史君、グローバル文化学環の4年生二人と共に、はじめて被災後の陸前高田を訪れた時、瓦礫で埋め尽くされた街の跡に立って、ここにあったはずの見慣れたものがないことに、奇妙な現実感のなさを覚えました。翌日、一関から東京に戻るときも、昨日見た風景は夢だったのではないか、今戻れば、きっと昔の風景がそのままあるに違いないと後ろ髪をひかれながら車に乗り込んだことを覚えています。
連休明けに、我々の訪問の報告をグロ文緊急セミナーとして実施したとき、小さな教室に溢れるほどの学生と教員が集まりました。自分たちも被災地の支援に関わりたいと強く望んでいるお茶大生たちがたくさんいることがわかりました。お茶大生に、いったいどのような支援ができるのだろう、というのが私たちの問いになりました。
「カフェでもやったらどうだろう」というのは、一緒に行った内海先生のアイデアでした。コーヒーを淹れて、癒しの場を提供し、じっと話を聞く。瓦礫の片づけは難しくても、そんな場所が創れれば、お茶大生も役に立つかもしれません。6月に2度目の訪問をしたとき、陸前高田市役所で仮設住宅のリストをもらい、米崎小学校(父の卒業した学校です)校庭につくられた仮設住宅地の代表者の方のお宅を、飛び込みで訪問しました。
佐藤一男さんという40代の「漁民」(名刺にそう刷り込んであります)の方に話をぶつけると、大歓迎という答えが返ってきました。仮設住宅地には、高齢者の独り暮らしなども多く、なかなかコミュニティができないのが問題で、市役所は集会所を建ててくれないので、NGO(セーブ・ザ・チルドレン)に建設を引き受けてもらったばかりとのこと。そこにカフェができれば、皆集まりやすくなるというわけです。しかも佐藤さんは、大のコーヒー好き。最初からお互いに意気投合した出会いでした。
7月の3回目の訪問で段取りを作り、9月9日~11日にコミュニィカフェ「お茶っこ」をオープンすることができました。「お茶っこ」というネーミングは、岩手弁のお茶(「お茶っこ飲んでいくべし」といった感じで使います)と、お茶大の娘たち(お茶っ娘)をかけています。コーヒーを淹れる機械とコーヒー豆(千杯分)ほかは、内海先生がいつも生豆を買う東京のコーヒー卸売業者ワイルド珈琲の社長の天坂信治さんが寄贈してくださり、自らキャンピングカーを運転して陸前高田まで届けてくれました。
9月10日のオープニングには、大学院生で岩手の葛巻町出身の中村雪子さん、その友達で画家のうすむらさおりさん、グロ文4年生の新井さんと奥住さん、内海先生、グロ文の同僚の三浦先生が加わり、さらに内海先生の息子さんで岩手大学のマンドリンクラブのOB、仕事の合間を縫って仲間と被災地への慰問演奏を続けている内海祥治さんも駆けつけてくれました。集まってくれた仮設住宅のおばさんたちは、思いのほか明るく、極限の体験をした人たちの力強さを感じました。しかし集会所にやってこない人たち(特に高齢男性)もたくさんいて、実はそうした人たちこそ深刻な思いを抱えているのだろうと思います。
陸前高田市の復興は10年はかかるでしょう。しかし建物や街並みは復元できても、家族や家、生活の場所や懐かしい風景を奪われた人たちの思いや喪失感を埋め合わせることはできません。その思いをわれわれが簡単に聞き取ることはできないし、また安易に尋ねてはいけないと思っています。カフェに参加する学生たちには、「問わず語り」に耳を傾けるように言い聞かせています。自らの拠り所となる人と場所と縁を奪われた人々に他所からの人がかかわって新しい場所と縁を作ることで、その元気を回復していくことができるかもしれません。何度も繰り返し訪ねること、そこから少しずつ新しい関係が生まれていくでしょう。これからも、このカフェは継続していきたいと思っています。
(お茶の水地理学会会報60号.2011年10月刊)
② パプアニューギニア、クラインビット村への訪問とクラインビット村支援会
私が1986年以来通っている、パプアニューギニア奥地(セピック川南部支流域)の村がクラインビットです。ブラックウォーターという湖(氾濫原)に面した美しい風景の場所で、人口は500人強。主食はサゴヤシ澱粉で、副食は湖の魚、森で獲れる野豚や火喰鳥、サゴヤシの木で育てる甲虫の幼虫(ビナタン)など。私は、2013年9月で15回目の訪問となります。
この村に2008年に手作りの小学校(低学年のみ)が立ち上がりました。それまで手漕ぎカヌーで1時間くらいかかる隣村(しかも他部族)の学校に通っていて、部族間の争いが起こると学校に行けなくなってしまうこともあったクラインビットの人たちにとって、自前の小学校は悲願でした。学校では、高校を出たボランティアの村人が教えていますが、正式な学校として認可されるには、正規の教職の訓練を受けた教員が必要で、その教習にはお金がかかります。その支援をしようと考えました。2009年4月に「クラインビット村支援会」を立ち上げ、お茶の水女子大学地理学教室の教員と卒業生でつくるお茶の水地理学会の方々に支援を呼びかけました。この支援会の活動は、2012年3月で終了しましたが、小学校は順調に発展しています(写真)。
以下、お茶の水地理学会の会報57号(2010年10月)・58号(2010年3月)、62号(2012年10月)に掲載した、これまでの活動報告の抜粋を掲載します。
村までの旅(2009年8月)
日本を発ったのは、2009年8月22日でした。成田空港から毎週1回(今年の3月から2回に増便)ニューギニア航空の直行便が出ていて、土曜夜に成田を発ち、日曜の朝まだ暗いうちに首都ポートモレスビーに着きます。今回の同行者は、立教大学の野中健一さん。アクティブな文化地理学者で、昆虫食の専門家として名高く、『虫食む人々の暮らし』(NHKブックス、2007年)等、多くの著書があります。今回野中さんが同行するきっかけは、名古屋大の岡本耕平さんが代表者の科研費(「海外フィールドワークにおける地理的知の還元モデルの構築」)で、2009年3月、メンバーの野中さんや池口明子さん(横浜国立大)たちの調査地ラオスのドンクワーイ村を訪ねたことでした(この訪問には、科研メンバーの森本泉さん(41回生)、田和正孝さん(関西学院大)も同行)。野中さんは、コオロギ、フンチュウなど、村の多彩な昆虫食をふるまってくれ、虫にも「旬」(旨い時期)がある、ただ虫を食べるのと「虫料理」とは違う(下拵えに手間をかける)、など教えてくれました。世界の虫を食べ歩く野中さんの認知地図の中でニューギニアが空白になっていると聞き、お誘いすると、ぜひ連れて行ってほしいということになりました。
今回のクラインビット村の訪問は、私にとって1986年にはじめてこの村を訪ねて以来10回目です。昨年は私が最初にパプアニューギニアの土を踏んでちょうど30年目でもありました。そこでこれまでの村の調査の成果を少しでも村人に還そうと考え、これまで長年撮りためた写真を組み合わせて、パワーポイントで20枚ほどのスライドを作り、それをA3サイズのポスターにカラー印刷して、紙芝居用に仕立てて持参しました。
23日の日曜は、車で野中さんに町の市場などを案内した後、ポートモレスビーに泊まり、翌24日の月曜に国内線でウェワクに移動しました。宿泊先のウェワクホテルは、1984年に民族学博物館の故吉田集而さんや私と同年代の文化人類学者たちと、科研でセピック川支流域の調査を始めた時からの常宿です。支配人の川畑静氏は、特攻隊の生き残り。80を超えた今もエネルギーに溢れ、太平洋戦争の激戦地で戦跡巡礼の日本人客が絶えないこのウェワクの地で老朽化の進むホテルを守り続けています。
クラインビットの村人には、あらかじめ到着の日を手紙で伝えておいたので、午後にはホテルを訪ねてくれました。私の長年のホストファミリーの家長でもう齢70近いアントン、次男のジャスティン、最初の訪問の頃からカヌーの操縦を担当してくれているギルバート、その奥さんで村の女性のリーダー格のジェリリンらと、再会を喜び、昨年撮った写真を渡し、早速旅路の準備です。まず手に入れるべきはガソリン。モーターカヌーでの村との往復に44ガロン入りのドラム缶2本(計7万円近く)が必要です。それにモーターの部品、エンジンオイルなど。ギルバートが必要な部品のメモを作ってきてくれていて、領収書をもらうよう言ってお金を前渡しします。
25日(火)は、朝から町の小さなスーパーに出かけて、食料品の買い出しです。オーストラリア産の米に、コンビーフやサバの水煮の缶詰、朝食用のクラッカー、玉ねぎ、砂糖、紅茶…など、あらかじめ作った買い物リストに沿って、汗だくになりながら買いこみ、段ボール箱に詰めます。パプアニューギニアの物価は日本とあまり変わらず、アジア諸国に比べれば何もかも大変高いのが難です。コンビーフの缶詰が一缶300円近く、オーストラリ産の米も1キロ150円くらいですから、現金収入のない村人には高根の花です。村には店はないので、われわれが食べるよりは多めに買って、村人への土産の代わりにもします。ウェワクからは、パプアニューギニアで博士論文のフィールドワークを続けている広島大学の院生の新本万里子さんがメンバーに加わってくれました。新本さんは、セピック川の北側のマプリックにある村に住み込んで調査しており、村での共通語となるピジン語も達者なので、彼女に野中さんの通訳兼助手を依頼しました。
26日(水)の朝、迎えの村人を入れて総勢8名のメンバーがまずめざすのは、セピック川下流のアンゴラムの町。ウェワクからは、乗合トラックに揺られておよそ3時間半の道のりです。いざ出発という段になって、ギルバートが暗い表情でやってきました。何とウェワクのどこにもガソリンがないとのこと。給油船が今日着くので、夕方には入手できるらしいのですが、それを待つと出発が1日伸び、ただでさえ短い(5日間)村の滞在がさらに短くなってしまいます。一瞬迷いましたが、到着後アンゴラムの町でガソリンを買えるわずかな可能性に賭けることにし(パプアニューギニアではいつどこで何が起こるか、実際に行ってみないと分かりません)トラックに乗り込みました。

乗合トラックの前で(野中健一さんと)
しかし結局アンゴラムにもガソリンはなく、ギルバートにウェワクに戻ってガソリンを仕入れてきてもらうよう頼み、われわれはアンゴラムで待つことにしました。予定外の宿となった(普段は夜寝るだけなので村人の知り合いの家などに寄宿します)アンゴラムホテルは、1980年、私がパプアニューギニア大学の留学生時代、はじめて一人で国内旅行をしたとき泊まった場所。高台のすばらしい立地にあり、昔は格式のあるホテルだったのですが、放漫経営で維持管理がなされず、今は見る影もありません。おまけに町中停電のため、シャワーもトイレも雨水タンクからバケツで水を汲んできて流さなければならないという有様。それでも40年間勤めているという老コックがきちんとした西洋料理を作ってくれました。翌木曜日の午後、無事ガソリンを買って戻ってきたギルバートが合流。予定より1日遅れで何とか出発できることになりました。
28日の金曜日。いよいよクラインビット村に出発。村まではモーターカヌーで8~10時間の道のり。できるだけ朝早く出たいと、6時半に起きて再び荷造り。しかし朝食、チェックアウトを終えても、なかなかカヌーの準備ができません。待つこと3時間あまり。荷物を積み込んでカヌーが出発したのはもう11時半近く。しかしエンジンの調子がもうひとつで、結局またアンゴラムに戻って、モーター(船外機)を取り替えることに。再出発したのは午後1時半でしたが、また点火の具合がおかしいと、すぐに対岸で停船。メカに詳しい村人の助けを得て、最終的に出発したのはもう午後2時でした。
セピック川はパプアニューギニア第二の大河です。広い川幅。両岸はセピック平原の草原に変わり、時折草を焼く煙が空高く上る風景の中、単調な船旅が続きます。ココヤシの木が目に入ると、そこは集落。村の名前を確認しながら航程を確かめます。出発が遅れたため、セピック川を離れ支流に入ったのはもう日もとっぷり暮れる頃。クラインビット村のあるブラックウォーター川の入り口にさしかかったときは真っ暗になっていました。
ブラックウォーターは小さな川ですが、周囲は広大な氾濫原になっています。あいにくこの時は大雨が降った後で一面水没しており、地元の村人でも暗闇の中では正しい水路を探し当てることができません。幸い月夜で薄明りはありましたが、何度も浅瀬に乗り上げながら苦労を重ねて、ようやく村の灯(電気はないのでランプや焚火)が見えるところまでたどり着いたのは、もう夜の10時でした。
暗闇の中、大勢の村人や子どもたちが集まってきます。「クマガイ!」「プロフェッサー」と声が飛び交う中、救命胴衣を外し、カヌーから降りて村人と握手。いつも世話になるアントンとジャスティンの家に荷物を運び込んでもらい、ランプを灯して、家で預かってもらっていた灯油コンロでお湯を沸かし、インスタントラーメンとサバ缶の夕食です。夜中の1時を過ぎても周囲のざわめきは静まりません。ふだんは10時ごろには眠りに着く子どもたちも興奮した様子。ようやく蚊帳を吊り、眠りに着いたのはもう2時近く。高床式ワンルームの家で20人以上の大家族が寝起きするこのアントン家で、寝る時の蚊帳の中以外はプライバシーのない生活が始まることになります。
クラインビット村の暮らし
私が長年訪ねているクラインビット村は、ニューギニア島北部を流れる大河セピック川の南部支流域にあります。村は、ブラックウォーターと呼ばれる大きな湖に面していて、そこには、野生の水鳥が乱舞する美しい湿原が広がっています。
クラインビット村の人びとは、この湿地帯に自生するサゴヤシの澱粉を集めて主食とし、魚や森の動物を捕って暮らしています。この生業の基盤は、私がはじめてこの村を訪ねた20年以上前から変わっていません。電気はなく、明かりはランプだけで、外の世界の情報はラジオに頼るしかありません。しかし魚や動物は豊富で、日常の食糧には不自由しない、自給自足の暮らしが成り立っています。
村の人口は約500人。高床式の家に、大家族で住んでいます。私がいつも居候しているアントン家は、戸主のアントンとその奥さんメリアン、次男のジャスティン夫婦とその子供たちを中心とする3世代同居の家族です。直系の家族だけでなく、叔母さんや従兄弟たちあわせて15~6人以上が、床面積100平方メートルほどのワンルームの住居に同居しています。
村の朝は早く、一番鶏が鳴く6時前頃には、皆起き出します。蚊帳を畳み、灯油コンロを出してきて、お湯を沸かし、私たちはコーヒーとクラッカーの朝食です。ただしこれは私たちだけの贅沢な食事であり、家族は朝のひと仕事を終えた後、火はおこさずに、前の日の残り物などで済ませるのがふつうです。1日の食事はだいたい2回。日が暮れた後、夕食となります。家族の食事は、サゴヤシからとった澱粉(固めて壺に入れて保存してあります)を、少しずつ取り出し、水で湿らせてから、薪をくべた炉にかけ、土製のフライパンで焼きます。具の入らないお好み焼きのような焼きサゴはしっとりしていておいしいものです。これに炉で焼くか、野菜代わりの木の葉と一緒に煮た魚を添えて食べるのが、日常の食事です。私は村にいる間、サゴヤシや魚をもらいながら、夕食にはウェワクの町で買って持ち込んだ米とコンビーフの缶詰を使って何かしら料理を作ります。料理を作っている間中、子供たちの注目と期待の視線にさらされ続けます。自分たちの食べる分を皿にしっかり盛り付けた後、鍋ごと家族に渡すと、ジャスティンが、夕食時を狙ってやってきた客人や家族にきちんと分配してくれます。

朝食を作る(子供たちの視線を気にしながら)
女の仕事、男の仕事
ニューギニアの村では、だいたい女性の方が働き者です。クラインビット村でも、女性たちは、薪を集めに近くの森に行ったり、魚を取りに行ったり、調理をしたり、子供の相手をしたり、赤ん坊に乳をやったり、洗面器で水浴をさせたり、日中は何かしら仕事をしています。水辺に生える草を干して、それで籠(かご)やゴザを編むのも女性の仕事で、子供の世話をしながらでも手を動かしていたりします。それにくらべると日中は男たちの方が暇です。森に狩りに出かけるのはだいたい夜で、それも毎日行くわけではありません。
男たちの熱意は、日々の暮らしよりも、伝統的な儀礼や信仰に向けられているようです。クラインビット村の中央には、精霊堂(ピジン語で、ハウスタンバランと呼ばれます)があります。現在は再建中ですが、90年代までの精霊堂は、高床式の壮大な建物で、入り口や柱にはびっしり彫刻が施され、そこには成人の男しか入ることができませんでした。村の男たちは全員が、身体全体に小さなナイフで傷を付け、盛り上がった傷跡がワニの鱗のように見える成人儀礼を受けています。これを受けた人間だけが、一人前の男です。
精霊堂の中には、祖先からの木彫や竹笛などが安置されています。若い男たちが、タジャオと呼ばれる精霊に扮することもあります。全体は黒く、鼻先が長く伸び、目の周りに白と赤で化粧を施した仮面をかぶり、サゴヤシの葉で編んだ衣装を身にまとって、タジャオは突然村に現れます。タジャオが近付くと、子供たちは本気で逃げまどい、捕まった子供が木の枝で叩かれて大声で泣き声を上げるのを、周りの大人たちが見守るというのは、どこかナマハゲのイメージに似ています。むかし精霊堂の中で、このタジャオが身支度をしている途中の写真を撮ったことがあるのですが、村人からはこの写真は絶対に村へは送るなと言われました(普通の写真は次回に持っていかないと怒られるのですが)。この写真を見ると、タジャオの正体がばれてしまうからだ、と言うのです。日常生活を支える女たちに対し、伝統文化を守ることは男たちの生きがいなのです。
村人の悩み
豊かな自然環境の中で、クラインビットの村びとたちは、一見してゆったりと満ち足りて暮らしているかのように見えます。しかし村人にもいろいろ悩みがあります。最大の問題は、現金収入を得る機会がほとんどないことです。自給自足の生活なら、現金などいらないと思うかもしれませんが、そうではありません。村の中では作り出せない塩や、水浴のための石鹸、ランプをともすために必要な灯油など、最低限の必需品を手に入れるためにはやはり現金が不可欠なのです。
湿地帯にあるこの村では換金作物の栽培はできません。かつてサゴ澱粉や燻製にした魚を町まで売りに行っていくらかの収入を得ることもできたのですが、その頃経由していたセピック川中流のティンブンケの町からウェワクまでの道が、州政府の道路の維持管理の予算がなく使えなくなっているため、下流のアンゴラムの町まで遠回りしなければなりません。ガソリン代が値上がりする中で、町から遠くなってしまったクラインビット村では、サゴや魚を売りに行っても赤字になってしまいます。
町の上級学校に行くには、多額の学費(寮費を含む)が必要ですし、保健医療のサービスも十分ではありません。村の中には、政府が補助する救護所(aid post)がありますが、置かれている薬は限られていて、村人は、診察を受けたいときには、カヌーを漕いで1時間近くかかる隣村のカニンガラにある診療所(clinic)まで出かけていきます。大きな病気や手術が必要な時は、ウェワクの公立病院まで行かねばなりません。交通費がかかる上に、きちんとした治療を受けるにはさらに多額のお金が必要であり、あきらめてしまう村人も多いようです。
小学校での歓迎会と研究発表
昨年(2009年)の訪問は、私にとっていろいろな意味で節目となるものでした。修士在学中に初めてパプアニューギニアの土を踏んだのが1979年12月で、それからちょうど30年。またクラインビット村へはちょうど10回目の訪問でした。
それで、これまでのささやかな恩返しをしたいと思い、私がこれまで村で行なった調査の成果と写真を、村人用にパワーポイントのスライドで紙芝居風に仕立て、A3判のポスター16枚にまとめて持参しました。語りの原稿は、パプアニューギニアの人びとの実質的な共通語のピジン語です。
それを村人の前で正式に披露したのは、滞在の3日目、村の小学校主催のわれわれの「歓迎式典」の席上です。当日村人に導かれて、10時半過ぎに学校の敷地に到着すると、もう村人たちはシンシン(伝統的な踊り)の正装で待ち構えていました。迎えに来た踊り手の子供たちに花飾りを首にかけてもらい、踊りの列にまじりながら進むと、学校の校舎の前には手作りの舞台が設えてあり、椅子が並んでいます。私たちは、そこに客人として坐り、村人の歓迎のスピーチを聞きました。スピーチの番が来て、私は、日本の例を挙げて国の発展のために教育の果たす役割がいかに大切かを説いた上で(こういう時はしっかり愛国者になります)、今回の教員訓練への援助を公表しました。そして村人たちの目の前で2000キナ(約8万円)の現金を、校長に手渡しました(写真3)。皆の眼の前で、現金を示すというのはちょっとはしたない気がするかもしれませんが、パプアニューギニアではそううしないとこの金がうやむやになってしまう危険があり、衆人の監視が必要でした。
歓迎式典が終わって、私たちは手作りの教室に移り、そこで3人が写真を見せながらそれぞれ研究発表をしました。トップバッターの野中さんのテーマは「世界の昆虫食」。世界中で、いろいろな昆虫が食べられていること、昆虫は究極の自然食でいかに素晴らしい食べ物であることを(私がピジン語に通訳し)力説しました。新本さんは、自分がフィールドとするセピック川の北側のマプリクの自分の村の暮らしを語りました。同じセピック川の周辺といっても、暮らしぶりがずいぶん違うことに村人は興味を引かれたようです。
最後に私。長老から聞いたクラインビット村の長い歴史から始まり、自然と生業、伝統文化(女性や子どもたちの前なので、男だけの秘密は明かしませんでしたが)、村人が抱える様々な悩み、などを語りました。自分たちの村の話が語られるのを、皆興味深そうに、また真剣に聞いてくれました。とりわけ子供たちにとっては、耳にしたことのない村の歴史の話は新鮮だったようです。(何しろ当事者たちが聴き手ですから)ふだんの学会発表よりよっぽど緊張し気合が入りましたが、終えた時には心地よい充実感が残りました。

小学校での講義(2009年8月、野中健一撮影)
村を去る日
ガソリン騒動で村への到着が1日遅れたため、村の滞在は中4日となり、学校での歓迎会の翌日はもう滞在の最終日でした。ドライバーを務めてくれたギルバートは、前の晩に森に行って、見事に野豚を仕留めてきてくれました。その解体作業を見学し、おすそ分けの肉を得て家に戻り、私が醤油と砂糖とニンニクで照り焼き風に調理しましたが、素晴らしく美味でした。
その晩は、村人主催の夕食会。会場の家に着くと、村の主だったメンバーが集まっており、テーブルの上には、洗面器を皿代わりに、きれいに料理が並べられていました。スピーチを交換した後、蓋を取ってびっくり。メニューは何と虫づくしです。サゴヤシにつく芋虫のような幼虫(少量食べる分にはおいしいのですが)やその他の虫が、炊き立てのご飯の上に乗ったり、木の葉と煮込んであったりと、様々な料理法で並んでいます。前日の野中さんの講演の効果が大きすぎたようです。「魚や肉も好きだと言っておけばよかった…」とは野中さんの弁。
翌朝は、家族に別れを告げ、古着や小物などを一人一人に手渡し、記念写真を撮って、出発です。村の船着き場まで、皆が付き添って、村人が総出で別れを惜しんでくれます。これは、私がはじめて一人で村を再訪した時から、変わらぬ光景です。モーターのエンジンがかかり、ボートが村を遠ざかっても村人たちは手を振り続けていました。
クラインビット村支援会会計・活動報告(2012年10月)
パプアニューギニア、クラインビット村支援会の立ち上げを報告し、お茶の水地理学会会員の皆様に支援を呼びかけたのは、2009年の会報第55号と、同年5月30日のお茶の水地理学会の席上でした。2012年3月までという時限での基金の活動には、それから3年の間、たくさんの皆様からご厚志を頂きました。基金の活動を終了するにあたって、あらためてお礼を申し上げるとともに、この場を借りて同会のこれまでの会計報告と簡単な活動報告をさせていただきます。
1.クラインビット村支援会 会計報告
(1)収支内訳
| 収入の部 | 金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 2009年度(寄付金) | 80,000 | 13件 |
| 2010年度(寄付金) | 53,000 | 5件 |
| 2011年度(寄付金) | 206,000 | 3件 |
| 総計 | 339,000 |
| 支出の部 | 金額(円) | |
|---|---|---|
| ①古着送付料 2009年7月 | 5,000 | 9,900円の半額 |
| ②小学校への援助(第1回) 2009年8月 | 35,000 | 講習費1000キナ×2名=2000キナ (2009年換算70,000円)の半額 |
| ③小学校への援助(第2回) 2012年3月 | 200,000 | 講習費1000キナ*3.5名=3500キナ (2012年換算140,000円) 学校の資材(黒板、教員指導書ほか) 1500キナ(60,000円) |
| 総計 | 240,000 |
残金:99,000円
2.会計報告説明
(1)収入の部 皆様から頂いた寄金は、会費(年3000円)とその他の寄付金に分かれますが、その区別をされなかった方が多かったため(年3000円の会費を3年間きちんと送り続けてくださった方もお一人いらっしゃいます)ここでは一括して扱いました。件数は初年度が13件で最も多く、総額は3年度目が最も多くなっています。これは9回生の伊瀬美地子さんから20万円という多額のご寄付を頂いたことによるものです。伊瀬さんは、国際協力に役立ててほしいという亡くなられたご次男のご遺志により、このお金を寄託してくださいました。ここには一件ごとの寄付額、お名前は記しませんが、そのほかの方々も、それぞれの思いを込めてご厚志を寄せてくださっていると拝察します。
【支出の部】
- 2010年度の古着の送料については、以前会員のお一人からお預かりしていたものに私の家族の古着や靴を合わせて送ったものです(その後も何度か自前で古着は送っていますが、この初回の半額のみ基金を使わせていただいています)。
- 2009年8月のクラインビット村訪問(会報57号・58号に「クラインビット村への旅」前編・後編として掲載)の際に行った村の手作りの小学校への第1回目の寄付です。村の手作りの小学校の校長先生を務めるベトロ氏に、現在ボランティアで務めている村の若者を正式な教員として認定してもらうために必要な講習会の費用(1回1000キナ*二人分=7万円(当時))を寄付し、そのうちの半額3万5千円を基金から支出しました。(デリックとアンブロスの二人がこの資金を使って講習会を受けました。デリックは半額をとりあえず自費で賄うことができたため、その分の500キナは、学校の資材購入に使われました)
- 2012年3月のクラインビット村訪問時に、村のリーダーや小学校の先生たちと話し合い、クラインビット村支援基金から5000キナ(20万円)を学校に寄付することを決めました。その内訳は、まだ講習を受けられてない3名の先生(リンディ、ジョージ、シコラ。このうちシコラは女性の先生です)の講習費(1回1000キナ*3人分=3000キナ)と、前回半額自費負担したデリックの講習費.半額(500キナ)、そして残りを教室の資材費(新しい教室用の黒板、教員用の指導書など)に充てることにしました。
以上が支出報告です。
残金の99,000円については、これからの学校の展開をながめた上で、あらためて有効な寄付の方法を考えようと思っています。この点について、積極的なご意見やご提案があればぜひお寄せください。

小学校の授業風景(2012年3月)
2.村の学校と教育の現状
施設・教材などまだまだ足りないものを数えればきりがないのですが、村の小学校は、着実に育っていると感じます。校長のベトロは、村人の中では珍しく(?)しっかりした金銭感覚を持っていて、毎回村に行くたびに帳簿をみせてきちんと会計報告をしてくれます。2012年3月の訪問時に、教室の授業を参観させてもらったのですが、それぞれの先生が個性を生かした授業をしていました。たとえばジョージは几帳面な性格で細かすぎるくらい丁寧に指導していました。シコラは女性ですが3名の中ではリーダー格で、朝礼の国旗掲揚と国歌斉唱で生徒たちをきちんと統率していました。来年にはトレーニングを終えて修了書をもらった二人の教員が戻ってくることになっていて、小学校の公認のめどもついたとのことです。ボランティアの教員たちの顔も明るく感じました。
今年、村の初級学校の第3学年の教室が新設され、今までの3クラスから4クラスに増えることになっています。毎年一クラスずつ増やしていき、6学年まで村の中で教育を受けられるようにする予定です。そのあとは、隣村のカニンガラにある上級小学校に進んで7・8学年を学び、さらに希望者はハイスクールに進むことになります。ハイスクールは町や遠方にしかないため、寮等に寄宿することになります。
しかし問題はその費用が嵩むことで、年に学費と寮費をあわせて1000キナ近くかかるため、おいそれと学校に進むことはできず、進学しても途中で学費がなくなってドロップアウトしてしまうことも珍しくないようです。政府からの奨学金を得るチャンスも少ないようで、このあたりが、村の教育の今後の課題だと思います。
3.村への訪問と村人の変化
この3年間に、わたしはクラインビット村を5回訪れています。
第1回:2009年8月(村への滞在は5日間)、第2回:2011年3月(同5日間)、第3回:2011年8月(同7日間)、第4回:2012年3月(同4日間)、第5回:2012年8月(同7日間)。
このうち、第2回目・3回目の訪問は、野中健一さん(立教大学教授)を代表者とする科学研究費「微量元素から捉える環境利用と文化的適応の地理学的研究」(基盤研究A)の資金によるものでした。この科研メンバーの専門は、人文地理学者、自然地理学者、人類生態学、農学、保健学、水産学などさまざまです。ローカルな環境から栄養として摂取される微量元素が人間の健康にとって重要な役割を果たしているのではないかという仮説のもとに組織された研究グループで、メンバーの大半は、すでにラオスで共同調査を重ねてきています。ニューギニアを調査地に選んだのは、2009年に野中さんが私とクラインビット村を訪ねたときに、彼がこの村を気に入り、ぜひまた調査に来ようということになったのが発端でした。クラインビット村がニューギニアの中でも奥地にあって、現金収入がなく、伝統的な自然資源に食料を依存しているということも重要な条件となりました。
2011年8月に計画した大勢のメンバーの共同調査を実現するためには、クラインビットの村人の協力が必要でした。医学的な調査を含むこともあり、パプアニューギニア政府に英文の調査申請書を提出し、調査許可の申請をしたのですが、村人がまず調査の趣旨と意義を理解してくれ、調査に協力する意思を表明してくれることが、調査を認可させる条件になります。3月にまず前にこの村を訪れている広島大学の大学院生の新本さん、彼女の調査助手のポールとともに村を訪ねて、調査協力の依頼をするとともに、大勢の調査メンバーが共同で寝泊まりできる家を作ってほしいと頼みました。無事クラインビットの村人から承諾を得て、家の建設を若者リーダーのティムソンに委ねました。彼は必要な資材を釘の数まできちんと計算してリクエストし、私たちはウェワクまで同行したカヌードライバーで調査助手のギルバートにその購入を頼んで、パプアニューギニアを離れました。

村のゲストハウス(2011年8月撮影)
果たして本当に家ができているのか正直不安でしたが、8月に私が先乗りして村を訪ねると8部屋もある立派なゲストハウスが出来上がっていました。後から二手に分かれてやってきた10名のメンバーたちは、伝統的な衣装に着飾った村人に肩車され村の広場でシンシン(踊り)の歓迎を受けました。メンバーたちが村で行ったのは健康と栄養の調査で、村人の血圧や簡単な採血を含む健康診断と身体計測をして健康状態を把握し、前日に何を食べたかを詳しく聞いてその食事を翌日に再現してもらい栄養価を量るという方法で栄養状態の調査をしました。村人の中から10人のある程度英語ができる調査助手を選んでもらい、村人からの聞き取りや計測の協力してもらいましたが、全員熱心に見事に務めてくれました。調査期間中にはこの調査のカウンターパートとなった東セピック州の保健局のアルバート氏も何人かの職員とともに、われわれの調査を見学に村まで足を運んでくれました。こんな奥地の村に、外国人や州政府の人間が大挙して押し寄せるなどということは、今までなかったことで、村人たちも誇らしげでした。

調査隊を肩車とシンシン(踊り)で歓迎する村人(2011年8月)
第4回目の訪問は、わたしが代表者となった科学研究費(基盤研究A)「ローカル・センシティヴなジェンダー地理学とグローバルネットワークの構築」によるもの、第5回目の訪問は、同じく私が代表者の福武財団の助成金「『場所に根ざす知』の共同構築を通じたフィールドワークの知的還元の実践――パプアニューギニア、クラインビット村」によるものです。2012年3月には、お茶大の学生二人を連れて(地理環境学コース修士2年生の志村多嘉子さんと、グローバル文化学環4年生の新井杏子さん。二人とも私が論文指導をした学生で、論文を書き終えた後に)クラインビット村を訪ねました。こんな奥地にニューギニアを研究するわけでもない普通の学生を連れてくる勇気は、今まではなかったのですが、ゲストハウスができたこと、村人との関係がうまくいっていることから思い切って試みてみました。ウェワクの町から車で4時間、モーターカヌーで8時間以上という道のりを1日でこなし、村滞在は実質4日間という強行軍でしたが、二人は帰るまでに村の言葉をいくつか覚えて挨拶をするまでになりました。村では、森でサゴヤシの木から澱粉をとるやり方を実地で学んだり、湖に魚取りにつれて行ってもらったりしました。寿司屋でアルバイトしたことのある志村さんは鱗取りを器用にやってのけ、褒められていました。二人は子供と遊んだり、村人に折り紙を教えたりと、すっかり人気者になりました。束の間ではありますが、文化を越えた交流の担い手となってくれたと思います。

写真左:サゴヤシを採る 写真右:折り紙を折る(2012年3月)
印象的だったのは、われわれが彼らの生業や食事や薬草などのいわば伝統的文化に注目して調査したり、学生たちが村人の暮らしに関心を寄せたことで、村人が喜び元気になったように感じられたことです。私はクラインビット村を訪ね始めた最初の6-7年ほどは、もっぱら村の歴史や社会・文化を長老から聞き取っていました。しかし何回も通ううちに、村人の要求もあって村の「開発」観をめぐる聞き取りが中心になってきました。しかし、それは結果的には、村人に自分たちの村に足りないものは何か(地元学の吉本哲郎さんの言うところの「ないものねだり」)を焦点化させる結果になっていたのかもしれないと反省させられました。
パプアニューギニアの調査は、距離的に遠いだけでなく、費用が嵩みます。航空券代が国内線を含めて15-6万円、陸路は運転手つきの四輪駆動の車をチャーターして途中のセピック川まで半日の道のりで往復10万円、そこから村までモーターカヌーで約6-8時間の道のりがガソリン代だけでドラム缶1本=4万円以上、かかります。このほかにドライバーや調査助手を務めてくれた村人への謝金、ホテル代(今、ポートモレスビーのホテルは軒並み高騰していて、長年常宿にしているちょっとしたホテルが1泊2万5千円以上します)など合わせると、1回の調査で40万円は軽く飛んでしまう計算になります。
東南アジアなどと違って自費で気軽に訪ねるというわけにはいかないパプアニューギニアの辺鄙な村に3年間これだけ頻繁に通えたのは、幸運にも前述のような資金的裏付けに恵まれたからですが、このクラインビット村支援基金の後ろ盾も大きかったと感じています。齢を取ると、正直なところだんだん村の調査は肉体的にもきつく億劫になってくるのですが、村とその活動に思いを寄せてくださる人の存在をバックに、背中を押されるようにして通い続けたという実感があります。
あらためて遠く離れたパプアニューギニアの村に思いを寄せてくださったすべての方に、お礼を申し上げたいと思います。