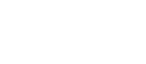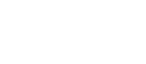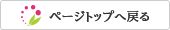- トップページ
- 文教育学部
- 人文科学科
- 哲学・倫理学・美術史コース
- スタッフ紹介(哲学・倫理学・美術史コース)
ページの本文です。
スタッフ紹介(哲学・倫理学・美術史コース)
2025年10月1日更新
スタッフ紹介
|
佐藤 有理 (さとう ゆうり) |
哲学 現代英米哲学と認知科学・AIの学際研究 現代英米哲学を担当しています。言語哲学、論理学/論理哲学、心の哲学、存在論、美学、社会哲学、行為の哲学、科学哲学、認識論などです(哲学史・非英語圏の哲学的伝統は含まれない)。これらと認知科学(AI、言語科学、脳科学、実験心理学、経済学など)の関わりのあるところに研究上の興味があり、人の思考・推論・判断の諸問題に学際的にアプローチしています。 |
|---|---|
|
池松 辰男 (いけまつ たつお) |
哲学 西洋哲学を担当しています。G.W.F.ヘーゲルの哲学を始めとする、近代ドイツの哲学を専門分野としています。 研究の目的は、第一に、西洋哲学史における古典であるこれらの哲学の内容を、テクストに即して適切に解釈、理解することです。第二に、その過程で、現代と将来の私たち自身に直結するような哲学的な問題を考えることです。実際に取り扱う問題は、私たちの存在の基盤にかかわるもの(意識、無意識、身体、習慣、言葉等)から、私たちの実践の基盤にかかわるもの(幸福、倫理、社会等)まで、多岐に及びます。これらの問題を、古典という「巨人の肩の上」に乗ることで、より広い視野から考えられるようになることが、研究の一番の意義です。 |
|
宮下 聡子 (みやした さとこ) |
倫理学 倫理と心理と宗教の接点を探るという問題意識から、主として西洋の思想にアプローチしています。 |
|
長野 邦彦 (ながの くにひこ) |
倫理学・日本倫理思想史 倫理学・日本倫理思想史を研究しています。近代以前の日本倫理思想においては、人と人との間における倫理に限らず、神や仏といった人ならざる存在との間における「倫理」が問われてきました。こうした思想について、テクストに内在しつつ解釈する作業を通じて、現代の私たちが自明の前提としている枠組みを問い直し、より原理的な問題について探求することを目指しています。特に、関係性および関係項を、スタティックな相の下に捉えるのではなく、出会い、別れ、ときに再会してゆく過程において生成し変容する出来事として記述する物語的な側面に注目し、そこに表れている哲学的・倫理学的な問題について考えています。 |
|
土谷 真紀 (つちや まき) |
美術史学 日本美術史を担当しています。作家や作品の分析を通じて、造形が社会や人々とどのように関わってきたのかを考えています。 |
| 内山 尚子 (うちやま なおこ) |
美術史学 西洋美術史を担当しています。芸術家が旅や移動を通して「他者」をどのようにイメージし、そのイメージは周囲からどのように受容されるのかについて、「人種」やエスニシティの観点から「マイノリティ」と区分される芸術家の事例を中心に研究しています。アメリカ合衆国の20世紀美術が専門ですが、トランスナショナルな実践と作品、その意味を検討するため、周辺諸国諸地域の芸術動向との関係性も視野に入れ、ジェンダーやポストコロニアリズムを含む多様な観点から分析を試みています。 |