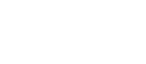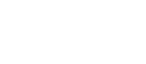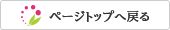ページの本文です。
教員紹介
2025年8月7日更新
杉野 勇(すぎの いさむ)
社会調査法、法社会学

理論研究・学説研究や帰責(責任帰属)の様式、女性の階層状況やWork Life Balanceについての計量分析に携わって来ましたが、近年は社会調査方法論や社会科学研究法に関心を持っています。教育面では、理論的研究と経験的データ分析を重視しています。
宝月 理恵(ほうげつ りえ)
健康と病いの歴史社会学、近代家族論

身体の衛生的ケアや病気予防への配慮が、近代統治とどのように結びついてきたのかを考えてきました。行政、専門家、家族、企業、メディア、慈善団体など様々なアクター、あるいは科学知や技術がどのように介在しながら私たちの身体規範や健康観を形成していったのか、「主体性」や「経験」をキーワードとして、インタビュー調査や言説分析から検討しています。
(2023年4月1日着任)
三宅 雄大(みやけ ゆうだい)
社会政策、社会福祉学

社会政策・社会福祉学を専門としています。とりわけ、法律・行政通知等による制度研究と当事者の語りに依拠した調査研究を組み合わせることで貧困・低所得世帯/生活保護世帯の子ども・若者が直面している問題を分析し、それらに対応する制度・政策の在り方を追究しています。また、並行して、公営住宅団地に対するスティグマ、日本における「福祉の「ふさわしさ」 welfare deservingness」に関する共同研究を進めています。
(2021年4月1日着任)
Iris Issen(アイリス イッセン)
文化人類学、クィア論、国際移動論

「クィア」を交差的な分析カテゴリーとして用い、「越境する」人々に焦点を当てています。グローバル化とデジタル化の文脈において、国家的、文化的、時空間的、または身体的なボーダーを越境することが、シス・ヘテロ規範、レイシャライゼーション、ナティビズム、ナショナリズム、ファンダメンタリズムなどの社会的プロセスと文化的ナラティブをどのように形成し、またそれらによって形成されるのかを探求しています。
(2025年4月1日着任)