
「感染症リスク下での多文化共生に関するアンケート」を実施しました
2018年4月から2022年3月まで,日本学術振興会の科学研究費補助金事業として,基盤研究(A)(一般)「社会調査の困難状況に対応するコンピュータ支援型複合モード調査法の実装」(課題番号18H03649)の研究代表者をつとめています。
2019年度(2020年1〜2月)の調査結果
この調査研究プロジェクトの一環として,2019年度には「多文化共生とライフスタイルに関するアンケート」を実施しました(2020年1月〜2月,
2019年度のメインサイト,
結果報告)。一般有権者対象の調査に加えて,ほぼ同一の調査票でウェブモニター対象調査も実施することが出来ました(
結果報告)。調査に御協力を戴いた皆様には心より御礼を申し上げます。
2020年度(2021年3月まで)の調査実施
〈ウェブパネル追跡調査〉
2020年度は,1年前には全く予想もしなかった事態の中で調査テーマや設計を少し変更し,「感染症リスク下での多文化共生に関するアンケート」(一般有権者調査およびウェブパネル追跡調査)を実施しました。
まず手始めに,9〜10月にウェブパネル追跡調査を実施しました(
結果報告
)。調査の実施は,日本の代表的調査専門組織の一つである,
株式会社 日本リサーチセンターに委託しました。
〈一般有権者調査〉withコロナとデジタル時代の多文化共生アンケート
2021年1月には一般有権者調査を実施しました。調査実施は,日本の代表的調査専門組織の一つである,
株式会社 サーベイリサーチセンターに委託しました。情報保護に関しては「
プライバシーマーク」の認定を受けており,合わせて,
ISO(国際標準化機構)の制定した調査専門の国際規格である「
ISO20252:2012」を取得しています。個人情報管理に関しては万全を期しております。御協力いただいた皆様には改めて心より御礼申し上げます。
 調査主旨説明書
調査主旨説明書: 調査協力のお願いを受け取られた方はこの説明書・Q&Aもお読み下さい。
この調査の実施に関しては,お茶の水女子大学の
人文社会科学研究の倫理審査委員会に倫理審査申請を行い,調査倫理上問題がないことの承認を受けました

。また,大学の徽章の使用も正式に認可されています

。
調査研究組織
社会調査法研究会(調査企画)
研究代表者:杉野 勇(お茶の水女子大学 教授)
[著書,論文]

杉野勇, 2019, 「定性的社会科学の新たな展開と課題――質的比較分析と過程追跡」ダニエル・H・フット/濱野亮/太田勝造編『法の経験的社会科学の確立に向けて』信山社, 501-530.

杉野勇, 2017, 『入門・社会統計学――2ステップで基礎から〔Rで〕学ぶ』法律文化社.

杉野勇・俵希實・轟亮, 2015, 「モード比較研究の解くべき課題」『理論と方法』30(2): 253-272.
研究分担者:轟 亮(金沢大学 教授)
[著書,論文]

轟亮・杉野勇編, [2010]2017, 『入門・社会調査法――2ステップで基礎から学ぶ』〔第3版〕法律文化社.

斎藤友里子・三隅一人編, 2011, 『現代の社会階層3 流動化の中の社会意識』東京大学出版会.(分担執筆)

轟亮・歸山亜紀, 2014, 「予備調査としてのインターネット調査の可能性」『社会と調査』12: 46-61.
平沢 和司(北海道大学 教授)
[著書,論文]

平沢和司, 2014, 『格差の社会学入門――学歴と階層から考える』北海道大学出版会.

石田浩・近藤博之・中尾啓子編, 2011, 『現代の階層社会2 階層と移動の構造』東京大学出版会.(分担執筆)

岩井八郎・近藤博之編, 2010, 『現代教育社会学』有斐閣.(分担執筆)
尾嶋 史章(同志社大学 教授)
[著書,論文]

尾嶋史章・荒牧草平編, 2018, 『高校生たちのゆくえ――学校パネル調査からみた進路と生活の30年, 世界思想社.

Ojima, Fumiaki, 2014, Intergenerational earnings mobility in Japan among sons and daughters: levels and trends,
Journal of Population Economics, 27(1): 91-134.

佐藤嘉倫・尾嶋史章編, 2011, 『現代の階層社会1 格差と多様性』東京大学出版会.
小林 大祐(金沢大学 准教授)
[著書,論文]

小林大祐, 2015, 「階層帰属意識における調査員効果について――個別面接法と郵送法の比較から」『社会学評論』66(1): 19-38.

小林大祐, 2011, 「『フリーター』のタイプと出身階層」『理論と方法』26(2): 287-302.

小林大祐, 2004, 「階層帰属意識に対する地域特性の効果――準拠集団か認識空間か」『社会学評論』55(3): 348-366.
歸山 亜紀(群馬県立女子大学准教授)
[著書,論文]

歸山亜紀・小林大祐・平沢和司, 2015, 「コンピュータ支援調査におけるモード効果の検証――実験的デザインにもとづくPAPI,CAPI,CASIの比較」『理論と方法』30(2): 109-128.

歸山亜紀・轟亮, 2013, 「公募モニター型インターネット調査データと個別面接法調査データの比較分析」金沢大学学術情報レポジトリKURA.

歸山亜紀・鳶島修治, 2019, 「職場における自律性が仕事の満足度に与える影響――前橋市・玉村町住民サーベイの分析から」『群馬県立女子大学紀要』40: 53-64.
調査に関するお問い合わせ先(調査実施委託機関)
株式会社 サーベイリサーチセンター 世論・調査課/担当: 土屋・西浦
フリーダイヤル:

0120-362-851/受付時間:9:00〜18:00(平日)
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-5 KDX日本橋313ビル 6階

調査の目的
この調査の目的は,大きく2つあります。まずひとつ目は,そもそもは,現在の日本社会における,選挙・投票行動や政治についての意見と多文化共生社会についての態度との関係,そしてそれらと性別や年齢,社会階層などの社会的属性との関連の仕方を捉えることでした。外国人観光客や定住外国人が増加し,東京オリンピック・パラリンピックを目前に控えた現在の日本の政治状況や社会状況を読み解き,様々な人達が互いに尊重し合いつつ,安心して暮らしていける社会作りの今後を展望することを目指していました。しかしその後「新型コロナウィルス感染症(Covid-19)」の流行により世界的に情勢は一変し,東京五輪は延期され,2021年の開催も危ぶまれる状況になりました。しかしこのCovid-19は,国際関係や対外的意識には東京五輪以上の甚大な影響を及ぼすと考えられたので,目的を少し修正して,withコロナ時代の(感染症リスク下での)多文化共生意識を明らかにすることを目指します。
 〔もうひとつの目的は...〕
〔もうひとつの目的は...〕
インターネット社会において,社会調査の有効性や有益さを高める為の改善方法を探ることです。近年,個人情報に対する意識の高まりや多様化するライフスタイルによって,従来型の社会調査が難しくなってきており,より回答者の負担が少なく,協力してもらいやすい調査方法の開発が急務となっています。また,新内閣は「デジタル庁」を設立し,国際的にどちらかと言えば遅れていた日本のデジタル社会化を推進しようとしています。こうした情勢の下で社会調査においても重要性を増しているのが,コンピュータとインターネットを活用するデータ収集法です。「インターネット調査」や「ウェブアンケート」は急速に普及した一方で,そのデータの質や信頼性についての懸念が払拭されていません。また,現代日本においても,誰もがインターネットやコンピュータに日常的に慣れ親しんでいるわけでもありません。インターネットという手段を社会調査のなかにどのように適切に組み込んでいくべきなのかが世界的にも重要な研究課題となっています。
対象者の選び方
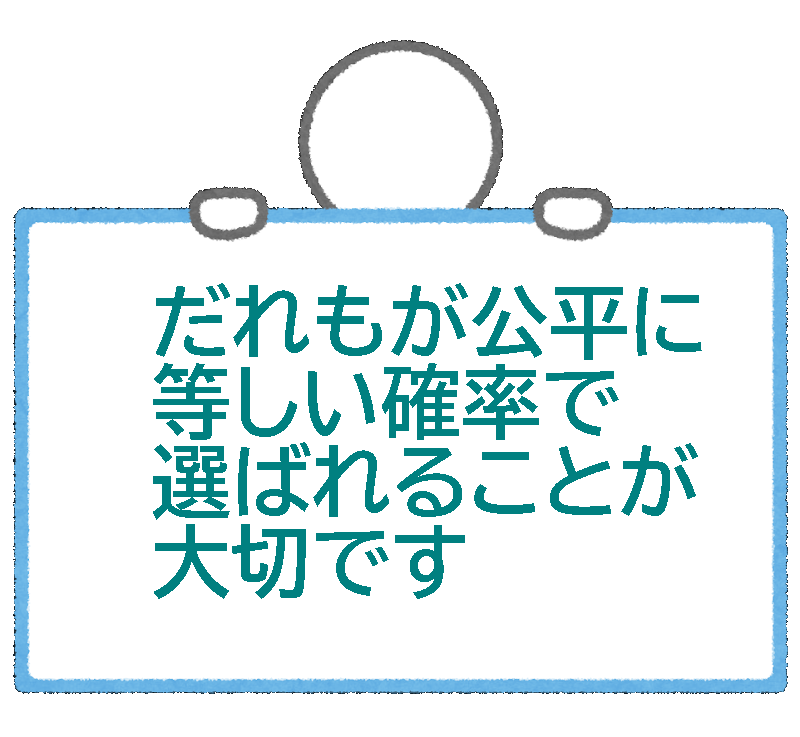 一般有権者対象調査は,中規模の社会調査として企画しており,東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知の1都4県,18歳から70歳までの日本人2,000名を対象としてします。調査をお願いする方は,二段階の無作為抽出という方法で選ばせていただいています(正確には「層化二段無作為(系統もしくは等間隔)抽出」といいます)。この方法は科学的な社会調査における標準的な方法であり,まずは地点を「くじ引き」に似た方法で全く偶然に(無作為に,ランダムに)選びます。そして選ばれた地点の中で個人を再び全く偶然に(無作為に)選びます。
一般有権者対象調査は,中規模の社会調査として企画しており,東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知の1都4県,18歳から70歳までの日本人2,000名を対象としてします。調査をお願いする方は,二段階の無作為抽出という方法で選ばせていただいています(正確には「層化二段無作為(系統もしくは等間隔)抽出」といいます)。この方法は科学的な社会調査における標準的な方法であり,まずは地点を「くじ引き」に似た方法で全く偶然に(無作為に,ランダムに)選びます。そして選ばれた地点の中で個人を再び全く偶然に(無作為に)選びます。
〔...より詳しく〕
今回の調査ではまず1都4県から50地点を無作為に選びます。そしてその選ばれた50地点について,選挙や政治などについての質問もさせて戴く為,各地点を担当する選挙管理委員会に選挙人名簿の閲覧申請をします(公職選挙法の第二十八条の三に基づいています)。閲覧が認められた各選挙管理委員会にて,各地点から40名の方を無作為に選ばせて戴きました。残念ながら選挙管理委員会から許可の出なかった2つの地点については,市区町村の役所に住民基本台帳の閲覧を申請して承認を受けました(住民基本台帳法第十一条の二に従っています)。
完全に無作為に選ぶという事は,「実際に誰が選ばれるかは全く偶然による」という事を意味します。「誰が選ばれるかは事前には全く分からない」のですが,これは「(選ばれた人ではなくても)誰が回答してもいい」という事では決してありません。厳密に科学的・統計学的な推論を行う為には,必ず「選ばれた人自身に回答して貰う」ことがどうしても必要です。「事前には誰になるか分からないが,一旦選ばれた後ではその人でなければならない」というのが大原則です。少しわかりにくいのですが,科学的に信頼に足る(言い換えれば決して捏造や誘導ではない)調査を実施する為に必要な条件なのだと御理解下さい。
調査の概要
実際に調査への御協力をお願いする時期(実査期間)は2021年1月から2月です。初めに複数ページの圧着ハガキで調査協力の依頼状をお出しした後に,改めて調査に必要な文書をお送りいたします。
社会調査・世論調査では,協力をお願いした方皆さんから御回答を戴けないと,集計結果が偏りを持ったものとなってしまいます。そのため,お願いした方の中から出来る限り多くの人の御回答を戴かなければならず,調査への協力のお願いを再送させて戴く事もあります。大変不快にお感じになられる方もいらっしゃると存じますが,このような理由を御理解戴き,御寛恕戴きたくお願い申し上げます。そして,出来ましたら一人でも多くの方に御協力戴けましたら大変有難く存じます。
〔...詳しく読む〕
調査への協力を御了承戴けましたら,Covid-19流行下での生活変化,様々な外国人・多文化に関する質問,選挙・投票に関する質問,政治についての御意見,ICT利用状況,生活状況や暮らし向き,基本的な属性などについての質問にお答え下さい。時間は人によって異なりますが,10分〜20分程度を見込んでいます。また,一見無関係に見える様々な質問が含まれているとお感じになられる方もいらっしゃるかも知れませんが,人々の意見や行動に影響しうる要因は極めて様々であり,そうした多くの要因間の連関を解明する為に是非とも必要な項目を厳選しておりますので,何卒御了承下さい。

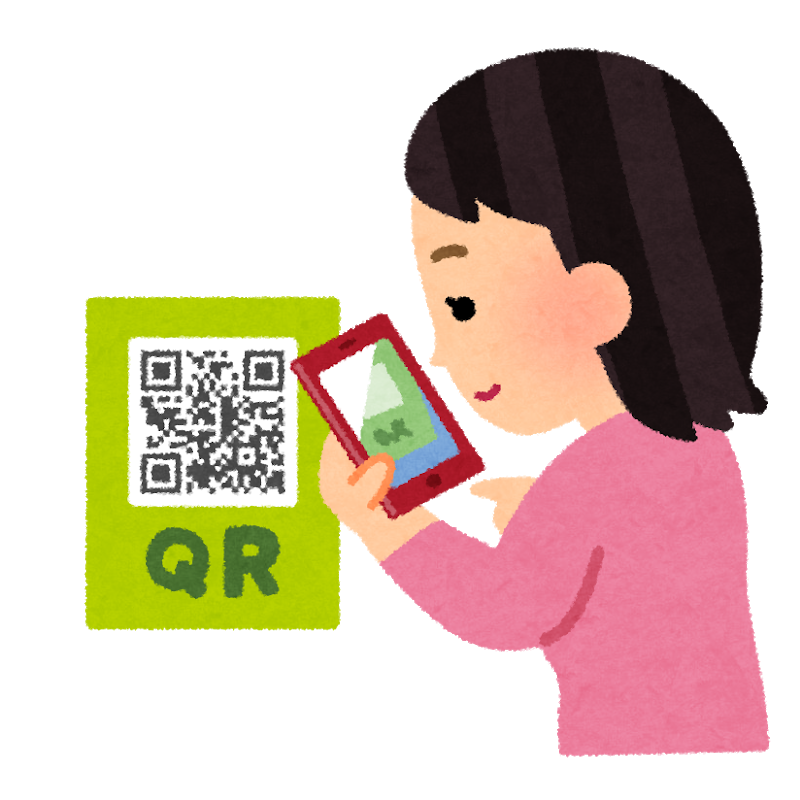

 )。調査の実施は,日本の代表的調査専門組織の一つである,株式会社 日本リサーチセンターに委託しました。
)。調査の実施は,日本の代表的調査専門組織の一つである,株式会社 日本リサーチセンターに委託しました。


 〔もうひとつの目的は...〕
〔もうひとつの目的は...〕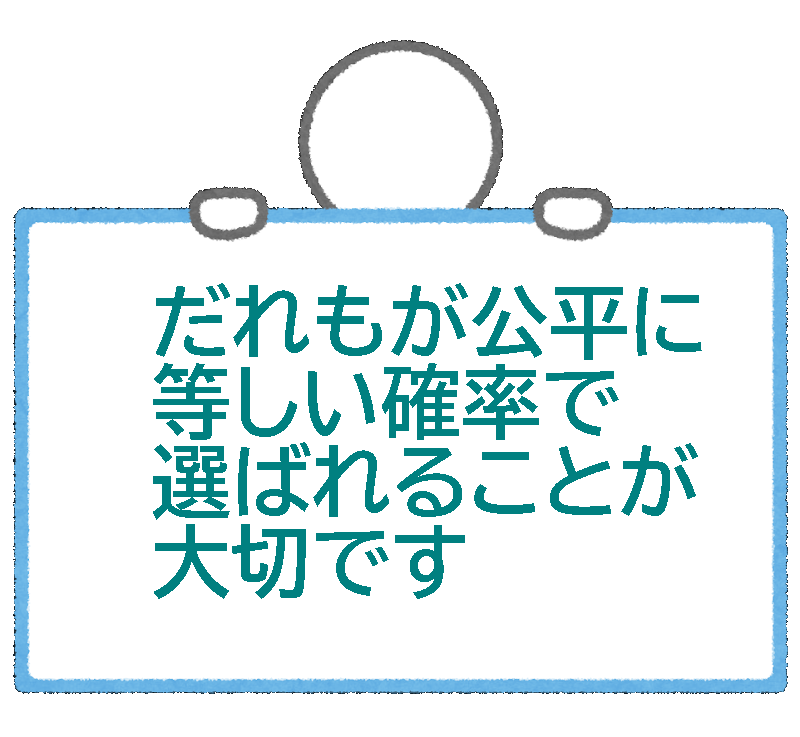 一般有権者対象調査は,中規模の社会調査として企画しており,東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知の1都4県,18歳から70歳までの日本人2,000名を対象としてします。調査をお願いする方は,二段階の無作為抽出という方法で選ばせていただいています(正確には「層化二段無作為(系統もしくは等間隔)抽出」といいます)。この方法は科学的な社会調査における標準的な方法であり,まずは地点を「くじ引き」に似た方法で全く偶然に(無作為に,ランダムに)選びます。そして選ばれた地点の中で個人を再び全く偶然に(無作為に)選びます。
一般有権者対象調査は,中規模の社会調査として企画しており,東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知の1都4県,18歳から70歳までの日本人2,000名を対象としてします。調査をお願いする方は,二段階の無作為抽出という方法で選ばせていただいています(正確には「層化二段無作為(系統もしくは等間隔)抽出」といいます)。この方法は科学的な社会調査における標準的な方法であり,まずは地点を「くじ引き」に似た方法で全く偶然に(無作為に,ランダムに)選びます。そして選ばれた地点の中で個人を再び全く偶然に(無作為に)選びます。
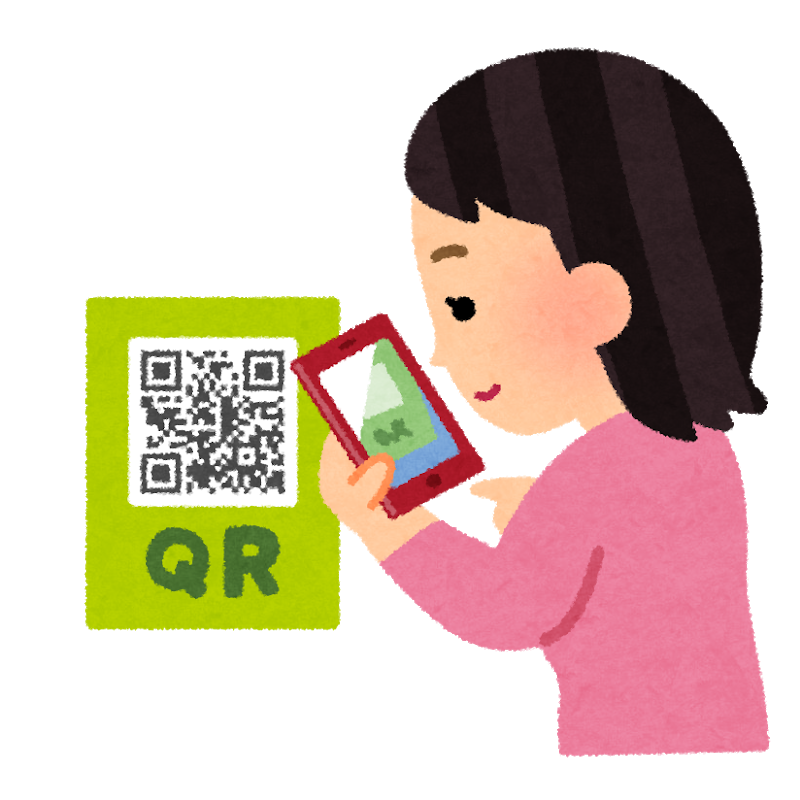
 杉野勇, 2019, 「定性的社会科学の新たな展開と課題――質的比較分析と過程追跡」ダニエル・H・フット/濱野亮/太田勝造編『法の経験的社会科学の確立に向けて』信山社, 501-530.
杉野勇, 2019, 「定性的社会科学の新たな展開と課題――質的比較分析と過程追跡」ダニエル・H・フット/濱野亮/太田勝造編『法の経験的社会科学の確立に向けて』信山社, 501-530.