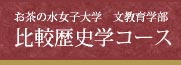|
|
ここしばらくは「植民地なき国の植民地主義」とナチズムの問題を関連させながら講義をしてきました。植民地に注目することで、16世紀から20世紀にいたる時代を大きくつかむことができます。また、他者とのかかわりで形成される、種主義、ナショナル・アイデンティティ、さらにはジェンダーの問題などもみえてきます。世界史を受験科目としなかった人たちにも、おもしろくて、興味がもてるような講義をするのはたいへんですが、思わぬ質問が歴史をとらえなおすヒントになるので、やりがいがあります。
ゼミでは、自分で問題をたて、材料を集め、分析し、他人にわかるようにまとめ、表現することを、西洋史というフィールドの特殊性をふくめて勉強します。解答
はひとつだけでないこと、ものごとにはいろいろな見方があることを知る場でもあります。そのためには参加者のやる気とサーヴィス精神、人とはちがったもの
の見方が重要になります。
「『模範植民地』青島が目指したもの−膠州湾租借地の目的と港湾、鉄道、鉱山開発」/「雑誌にみるナチの女性像−第二次世界大戦期を中心に−」/「バウハウスに見る近代モダニズム建築がもたらしたもの−ドイツと日本を例に−」/「『母の日』という戦略−ドイツと日本に『母の日』が定着するまで」/「マリア・テレジアと家族戦略」/「愛唱歌から見たナチ体制下の青少年」/「『国制改革』の精神と『自然観』−ハプスブルク帝国の2人の君主 マリア・テレジアとヨーゼフ2世の場合−」/「カントルと都市−18世紀前半のハンブルク市におけるヨハネウム・カントルの役割−」
|
![]()