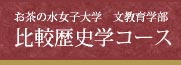|
 |
|
中東は、「西洋」(ヨーロッパ世界)と「東洋」(アジア)の中間に位置し、中東・イスラム世界の歴史を通して、現代世界の成りたちをさぐることをめざしています。特に、ダマスクスやカイロなど、イスラム世界の都市社会に関心をもち、都市の空間(ハード)と社会のしくみ(ソフト)の両面から、研究をしています。アラブ諸国に通いだしてはや25年、馬糞のにおいがしたカイロの下町も、高速道路がモスクのそばを横切り、アラビア半島のドバイには超高層ハイテク都市が出現し、アジアとアフリカとヨーロッパを結ぶハブ空港として24時間旅客が往来しています。最近は、イスタンブル(トルコ)、フェス(モロッコ)、サマルカンド(ウズベキスタン)、北京やカシュガル、ジャカルタなど、広くイスラム世界の町をめぐる、比較史に熱をいれています。
現代のパレスティナやイラクから、あるいは、アラビアン・ナイトやアラベスク模様から、中東の窓はあちこちに開いています。中東研究は世界各地に拡大、北京、ソウル、プサン、クアラルンプール、カイロ、アンマン、ベイルート、アンカラ、マインツ、バルセロナ、パリ、エクサンプロヴァンス、サンフランシスコ、アンカレジ、ワシントンなど、あちこちで開催される学会にでかけ、海外訪問国は25か国を数えます。2005年度から、グローバル文化学環と兼任、両方の講義を担当しています。2011年から、放送大学の講義「イスラーム世界の歴史的展開」を担当し、テレビ放送を通じてイスラーム史が学べるようになりました(その教科書も出版され、購入できます)。
|
![]()