|


ゼミは3・4年生が対象です。
少し前までは、鎌倉幕府のおこなった裁判の判決状を読んでいました。どの判決状もそれなりに面白いのですが、ひとつの事件や判決と、つぎの事件・判決とのあいだに連続性はないので、記録が読みたいという声があがってきました。それで、テキストを変更しました。
いま読んでいるのは、『満済准后日記』です。「まんさいじゅごうにっき」と読みます。満済は、京都醍醐寺のお坊さんで、将軍足利義持や、その次の義教などを補佐したひとです。ゼミでは、応永35年(=正長元年=1428年)の正月から読み始めました。義持が、お尻にできた腫れ物をお風呂のなかで不用意に掻き破って、それがもとであっけなく死んでしまうところからです。義持がまだ死んでいないのに、満済たちがさっさと見切りをつけてお祈り用の壇を片づけてしまうところでは、皆さん、義持にかわって憤慨しました。
いよいよ義教が登場してきました。くじ引きで選ばれた将軍です。この人はのちに「恐怖政治」を展開するようになりますが、最初のころは違います。どんな義教像が形成されるか、満済がじっさいにどのような役割をはたしていくのか、楽しみです。
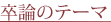 (近年分) (近年分)
ゼミで読む史料や、ここで行う報告は、あくまで「基礎体力」をつけるためのものです。卒論を書くときには皆さん、自由にテーマや史料を選びます。
「高台寺蒔絵と豊臣秀吉」
(蒔絵の発展と、秀吉による蒔絵の「政治的」な利用について)
「中世後期貴族層の葬送儀礼と習俗」
(「主人が亡くなると、カマドの神様も死ぬのです!」「・・・?」)
「下津八幡宮惣宮司と中世対馬宗氏の関係」
(対馬支配のキーとして宗氏は惣宮司の海上活動に注目した)
「足利義教期の唐物の贈与」
(セレブたちの超高級品の贈答、その実態と隠された目的)
「徳川家康神格化の成功過程とその受容に関する一考察」
(家康神格化の理論的背景に迫る)
「中世後期における女性の自立性」
(様々な文献のなかの女性の姿をみると、意外に・・・)
「中世前期における検非違使と穢れの関係性について」
(穢れとの関係の追究から見えてきた検非違使の三つ目の機能・役割とは)
「日本中世の病と宗教」
(この病には医者がいいのか、それともお祈りか・・・)
|

![]()