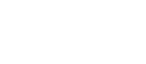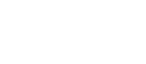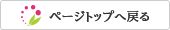ページの本文です。
実習について
2025年5月20日更新
「グローバル文化学環」の特長のひとつが「実習」です。グローバル化の問題を考え、理解するには、現場に出かけ、自らの身体や五感をフルに使って、考えることが必要不可欠です。地域理解や、文化間の交流や国際協力を、実際の現場で実践し、考えることがこの実習の目的です。三本柱に沿って、多くの種類の実習が用意されています。※実習内容は年度によって変わることもあります。
地域研究実習I
原則として、日帰りで年間5回程度、さらに連携している地理学コース主催の巡検を含めて10回以上開催される見学・実習に既定の回数参加することで単位が認定されます。複数年の間に参加することも可能ですが、その場合は既定の回数の参加を完了する年度に履修登録をしてください。
見学実習先は、日本におけるイスラームと東京ジャーミイ(モスク)、都市における歴史景観、博物館や宗教施設、都市と再開発など、多様です。実施時期と内容は、事務室前の掲示板へ掲示する他、グローバル文化学環の学生には随時メール等で案内します。
地域研究実習II
グローバル化は東京と地方とで、どのように異なって経験されているでしょうか。とくに地方において、グローバル化や国際化は、どのような機会と課題を与えているのでしょうか。地域研究実習 II では日本の大都市以外の地域におけるグローバル化の様子を探る目的において、北陸・東北・中国地方などを訪れます。2024年度は石川県金沢市を訪れ、グローバル化の様子とその経済的、文化的または社会的な影響について考察します。
本実習では①金沢市及び石川県の行政、地元の国際交流協会、地域経済の専門家の講演会、②金沢の伝統工芸品である久谷焼の商店や博物館の見学、③観光地にある商店街の調査、④金沢在住外国人との国際交流を通して、金沢市内の国際化・多文化への実況やその経済的または文化的な影響を知り、それらが東京とどのように異なるかを考察します。また、様々なアクターの見解を照らし合わせることで、グローバル化から得られる経済的及び社会的な影響が、同じ都市に暮らす所属や立場の異なる人びとにとって、どのように異なって経験されるのかを見極めることもできます。
多文化交流実習II・III
多文化交流実習IIでは、2016年以来お茶の水女子大学の協定校である、啓明大学や釜山外国語大学において、5~6週間にわたって実施される「複言語・複文化教育プログラム」に参加しています。このプログラムは前半には韓国の言語と文化を学び、後半には日本語教育実習を通じて、日本の言語と文化を教えるプログラムで、互いの言語・文化に対する理解を深め、東アジアがともに生きていくための、言語教育について考える場を提供しています。参加には4〜7月に開講される多文化交流実習Iを履修する必要があります(Iだけの履修は可能ですが、IIのみの履修は不可です)。報告書はこちら
多文化交流IIIは、海外協定校で実施される多文化交流の短期プログラムに参加することで2単位が付与されます。英語で行われるプログラムと日本語で行われるプログラムとがあり、2023年度は啓明大学とシドニー工科大学で、2024年度はシドニー工科大学で実施されました。
国際学生フォーラム
毎年、国際交流論として開講されています。海外の協定校の学生と国際的な問題解決のための討論を行います。第8回はアジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアの6大学の学生を集めて東アジアの共生を考えました。第9回以降はアメリカのヴァッサー大学との間でフォーラムを実施、環境問題(第9回)、COVID -19(第10回)、第二次世界大戦と平和教育(第11回)、多様性と包摂性(第12回)、などのテーマを扱いました。発表では日本側の学生は英語、海外の学生は日本語を用いて行います。